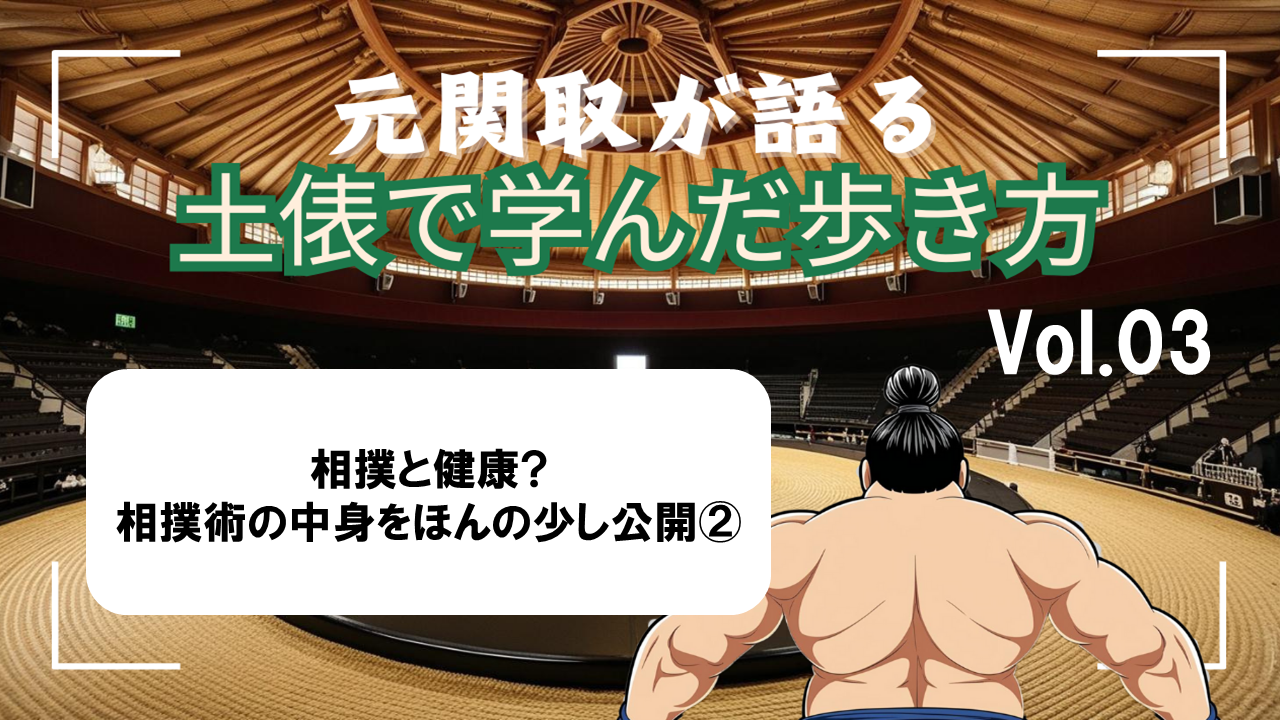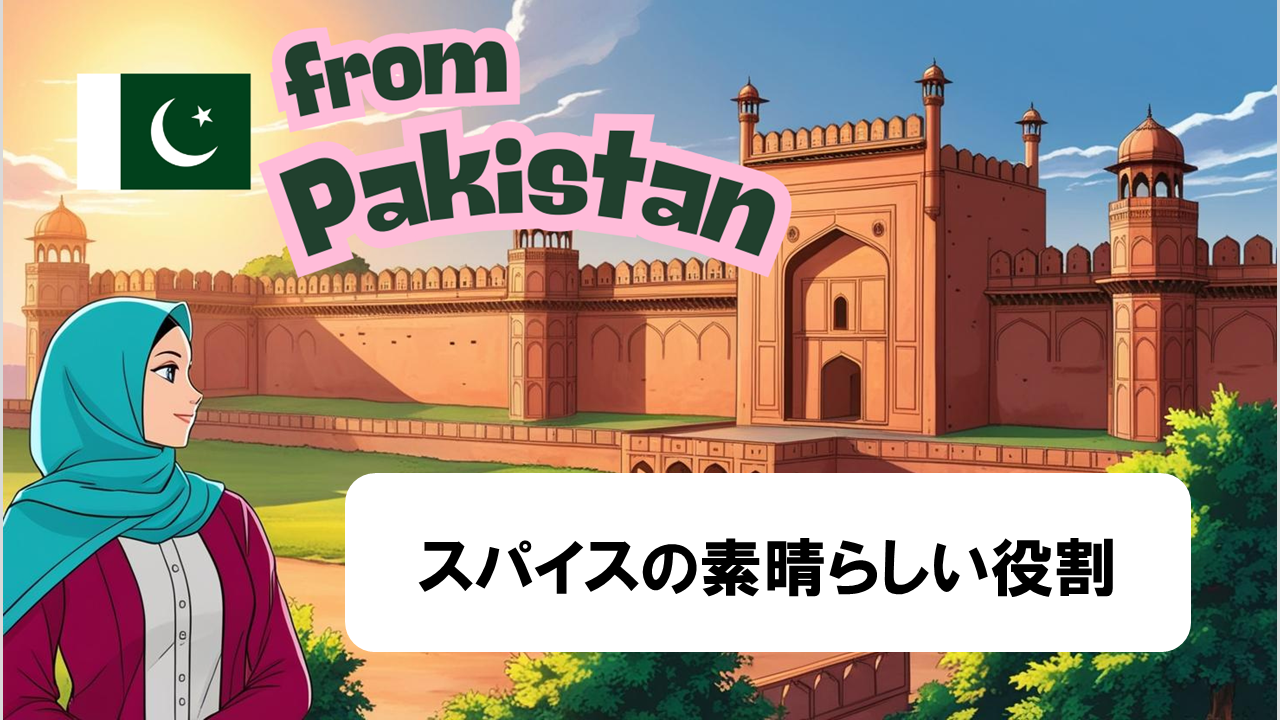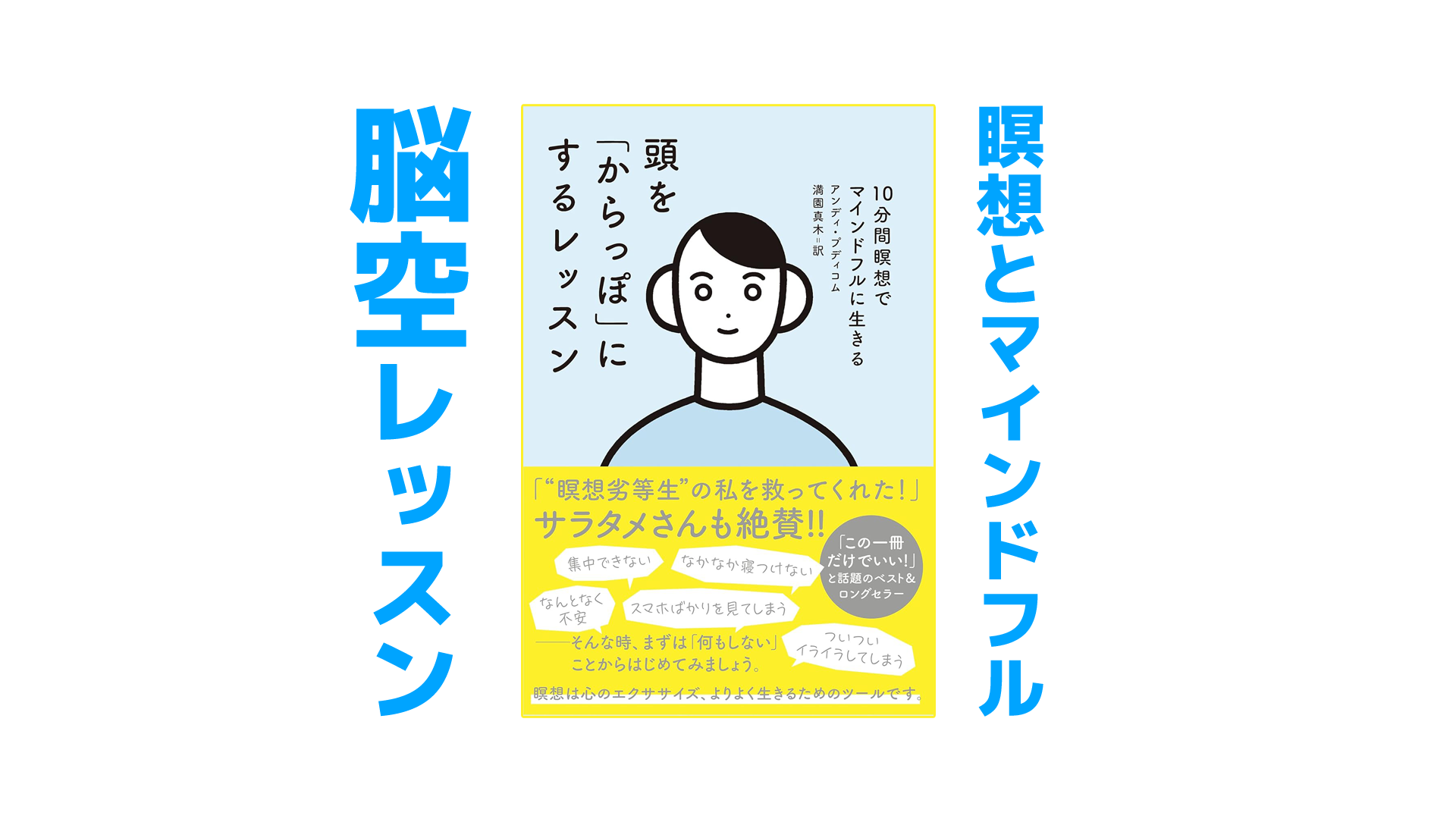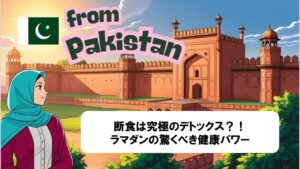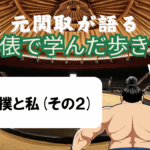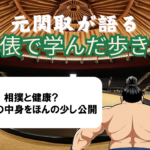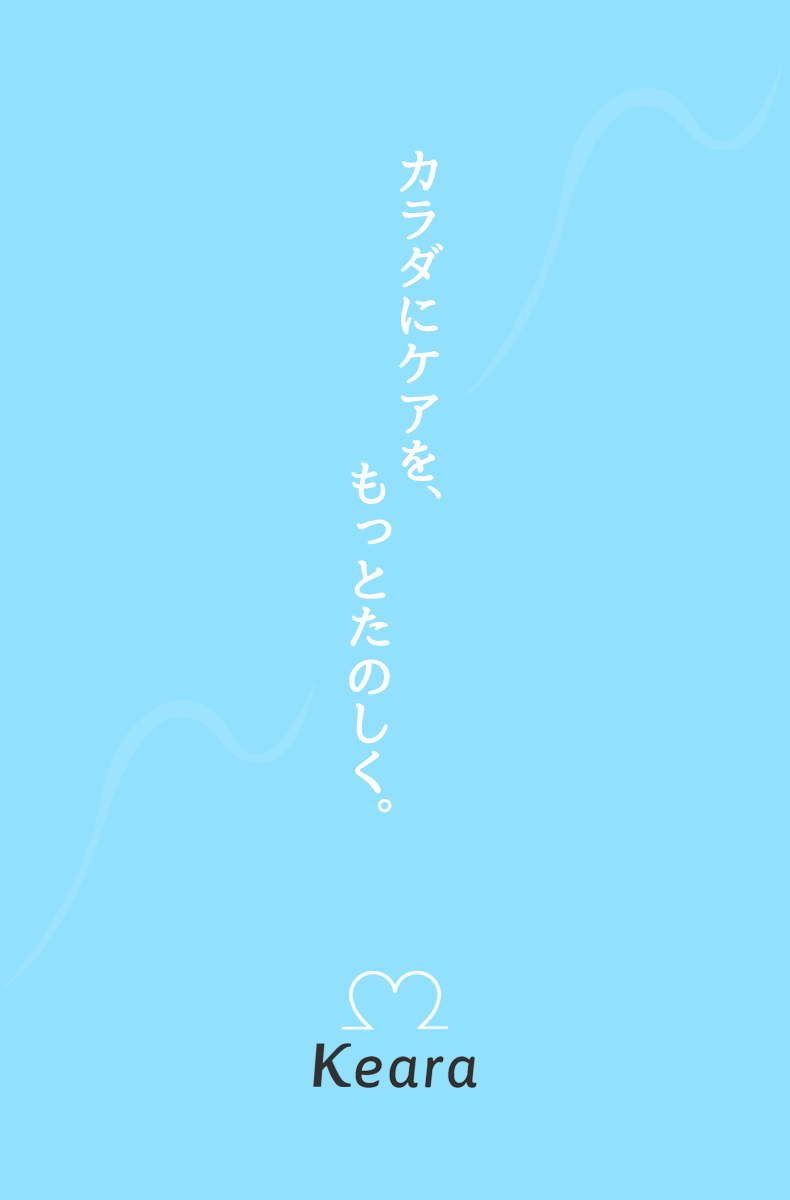腸活が大事なことは分かっていても「なにから始めればいいの?」「続かないかも」「難しそう」と感じていませんか。
実は、毎日の食事に簡単に取り入れられる腸活があります。それが「塩麹」と「醤油麹」です。普段使っている塩や醤油と置き換えて使うだけで、手軽に腸活を始められます。材料も2〜3つを混ぜるだけなので、ご家庭でも簡単に作れます。
麹は日本人の腸に合いやすく、腸内環境を整えてくれます。腸内環境が良くなると、免疫力アップだけでなく美容にも効果があるのです。また、料理を簡単に美味しく仕上げてくれます。
今回は、はじめてでも簡単に作れる塩麹と醤油麹の作り方と活用法をご紹介します。腸活は毎日続けることがとても大切です。無理なく続けられる腸活で、美容と健康を手に入れていきましょう。
旨み引き出す万能調味料!塩麹と醤油麹の特徴
塩麹と醤油麹は、腸内環境を整えながら、食材の旨みを引き出す万能調味料です。
麹は腸内の善玉菌を増やし腸内環境を整えます。また、タンパク質を分解し、食材の旨みを増やしたり、栄養価を高めたりします。
肉や魚と一緒に漬けておくだけで、肉を柔らかくし旨みを引き出すため、ただ焼くだけの調理でも美味しく仕上がります。また、スープを作る際に入れるコンソメの代わりに、塩麹を入れるだけで、無添加で旨みのあるスープに仕上がります。
炒め物の味付けとして使うだけでも、格段に美味しくなる魔法のような調味料です。

混ぜるだけ!簡単に手作りできる塩麹と醤油麹の作り方
塩麹と醤油麹は、材料を混ぜて発酵させるだけで作れます。市販もありますが、手作りすれば無添加で安心です。今回は、常温発酵と、発酵メーカーを使う2種類の作り方をご紹介します。できあがりの麹の粒が気になる場合は、ブレンダーなどで撹拌しましょう。
塩麹の作り方
【材料】
- 米麹・・・150g
- 塩・・・50g
- 水・・・200ml
米麹:塩:水=3:1:4の割合がおすすめです。
【作り方】
- 米麹と塩を手でよく混ぜ合わせる
- 清潔な容器に、1の混ぜた米麹を入れる
- 水を加えてスプーンで混ぜる
- フタを軽くしめて、1日1回混ぜて常温で1週間〜10日ほど置き、発酵させる
- できあがったら冷蔵庫で保存
【ポイント】
- 発酵メーカーを使用する場合は、60℃、6時間に設定してください。
- ほんのり甘い香りがして、麹が柔らかくなったら完成の目安です。
- 塩は、ミネラルを含む天然塩がおすすめです。
- 水はミネラルウォーターを使用しましょう。

醤油麹の作り方
【材料】
- 米麹・・・150g
- 醤油・・・300ml
米麹:醤油=1:2の割合がおすすめです。
【作り方】
- 清潔な容器に、米麹と醤油を入れて混ぜ合わせる
- フタを軽くしめて、1日1回混ぜて常温で1週間〜10日ほど置き、発酵させる
- できあがったら冷蔵庫で保存
【ポイント】
- 発酵メーカーを使用する場合は、60℃、6時間に設定してください。
- 麹が柔らかくなったら完成の目安です。
- 醤油は、こだわりのものを選ぶと、香りやおいしさを楽しめます。
- 水はミネラルウォーターを使用しましょう。

塩麹と醤油麹の活用法3選
塩麹と醤油麹は、普段使っている塩と醤油を置き換えるだけで、料理が美味しくなり、健康や美容効果を得られます。置き換える際の量や、使い方をご紹介します。
1.置き換えて使う
塩麹は、普段使う塩の倍量が目安です。塩小さじ1の塩分量は約6gですが、倍量の塩麹小さじ2の塩分量は約2gとなり、倍量使っても減塩になります。
シンプルな野菜炒めに、塩麹のみの味付けをしても、旨みの効果で物足りなさがなく美味しく仕上がります。
醤油麹は、醤油と同量が目安です。醤油も発酵調味料なので、風味豊かで旨みがありますが、醤油麹はさらに深みが増します。炒め物の味付けだけでなく、そのまま納豆や刺身などにかけて使えます。
2.肉や魚に漬ける
肉や魚などの食材に漬けることで、タンパク質が分解されて肉質が柔らかくなります。使う量は、食材の重さの10%の重量が目安です。たとえば、200gの肉を使う場合は、20g(大さじ1)の塩麹や醤油麹を使うと味のバランスがちょうど良いでしょう。
漬けて焼く、唐揚げの下味に使うなどといった使い方ができます。麹は焦げやすいため、火力を弱めて蒸し焼きにするか、クッキングシートを使うことをおすすめします。
3.コンソメの代わりに使う
コンソメの代わりにスープの味付けで使えます。300mlの水に対して大さじ1の量が目安です。ポトフやミネストローネは野菜と水と塩麹だけで作れます。そこに牛乳を足せばポタージュに。また、パスタソースやグラタンの味付けにも使えて万能です。
毎日使う調味料を置き換えて使うだけなので、簡単に取り入れられます。いろいろな調味料を使わなくても、塩麹や醤油麹だけで味が決まり時短にもなります。ぜひ、日々の食事に取り入れてみてください!
<関連記事>
塩や醤油もこだわって選びたい方は、過去のコラムもご覧ください。