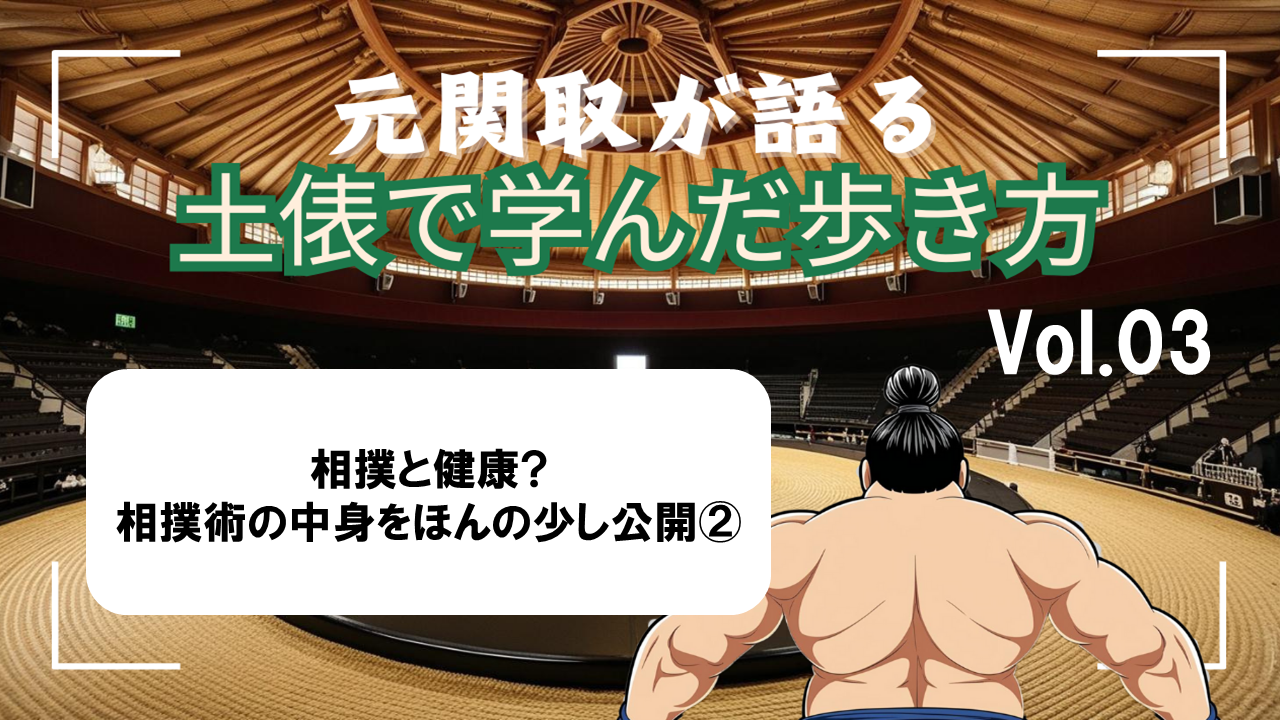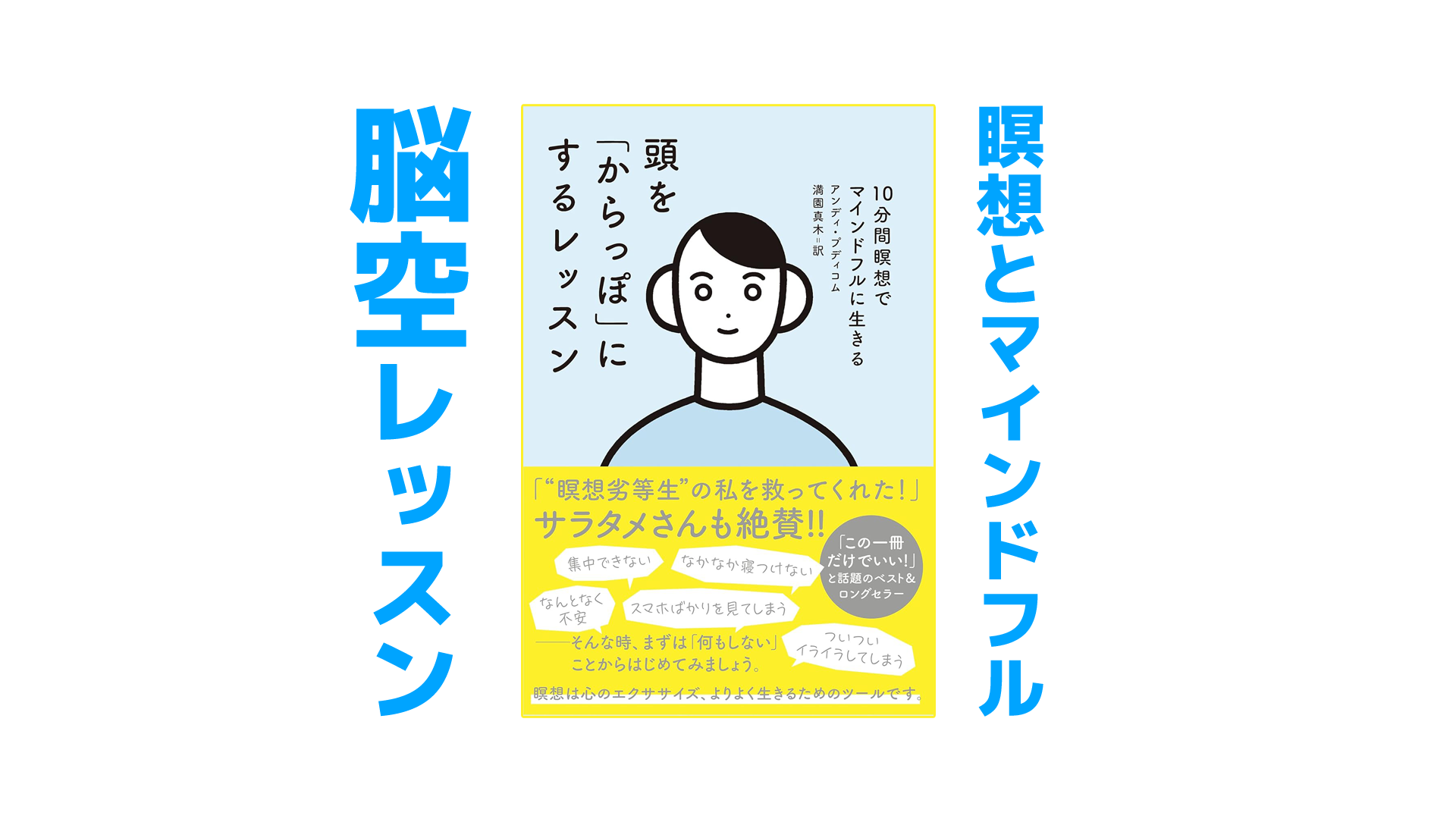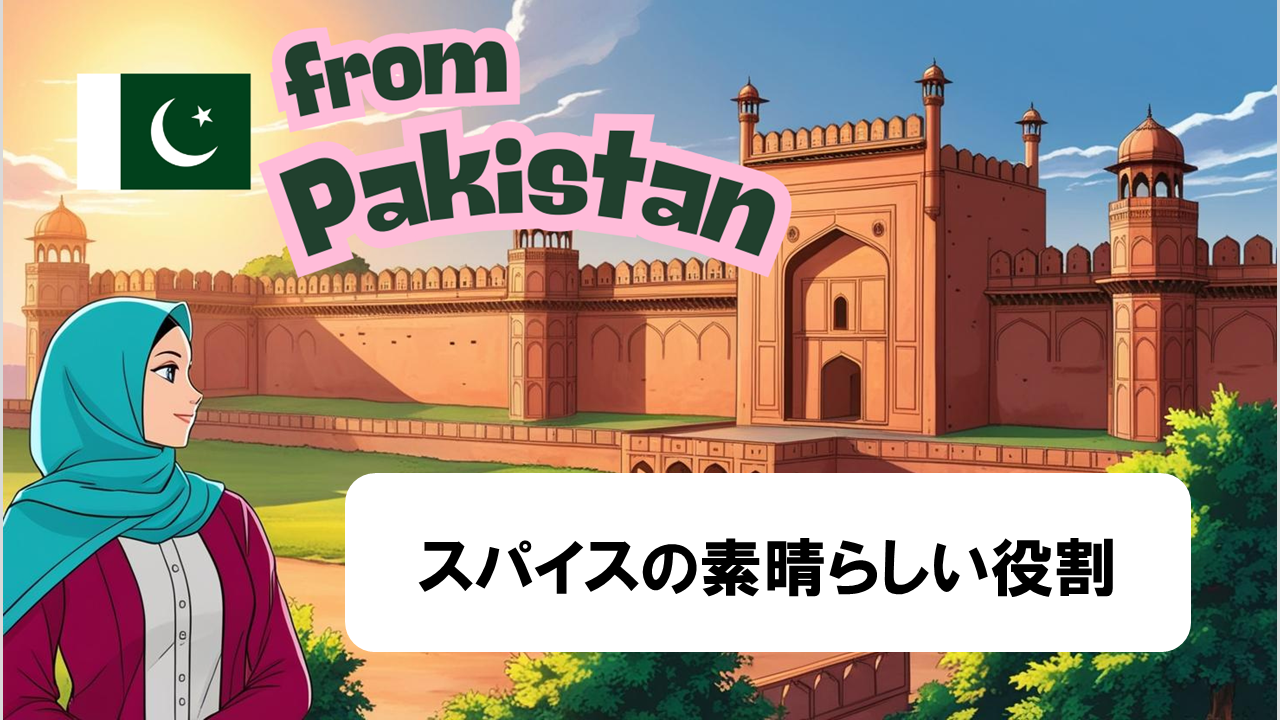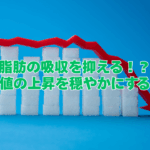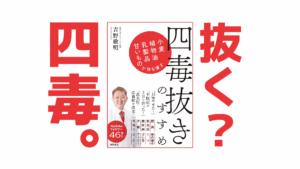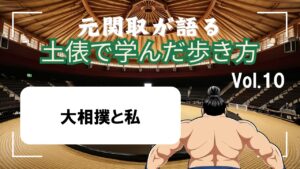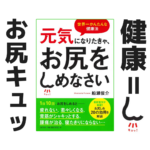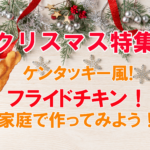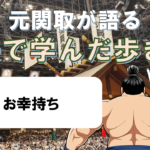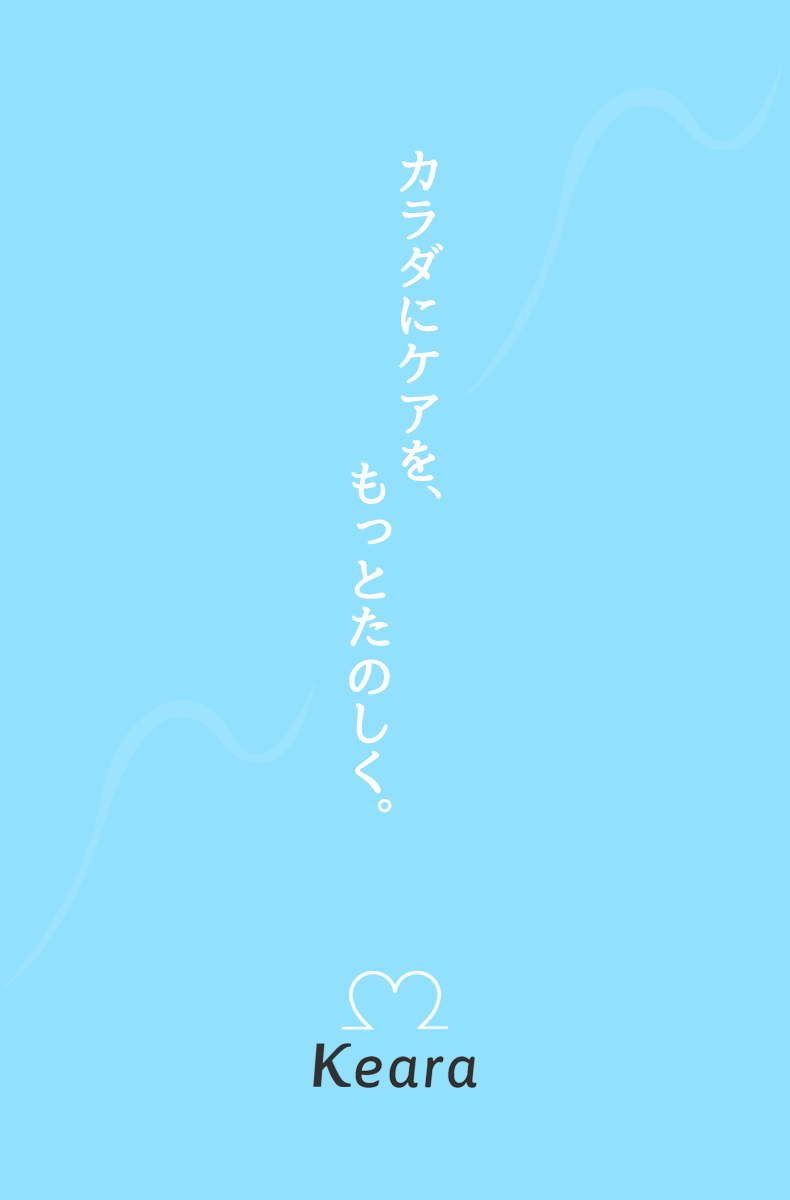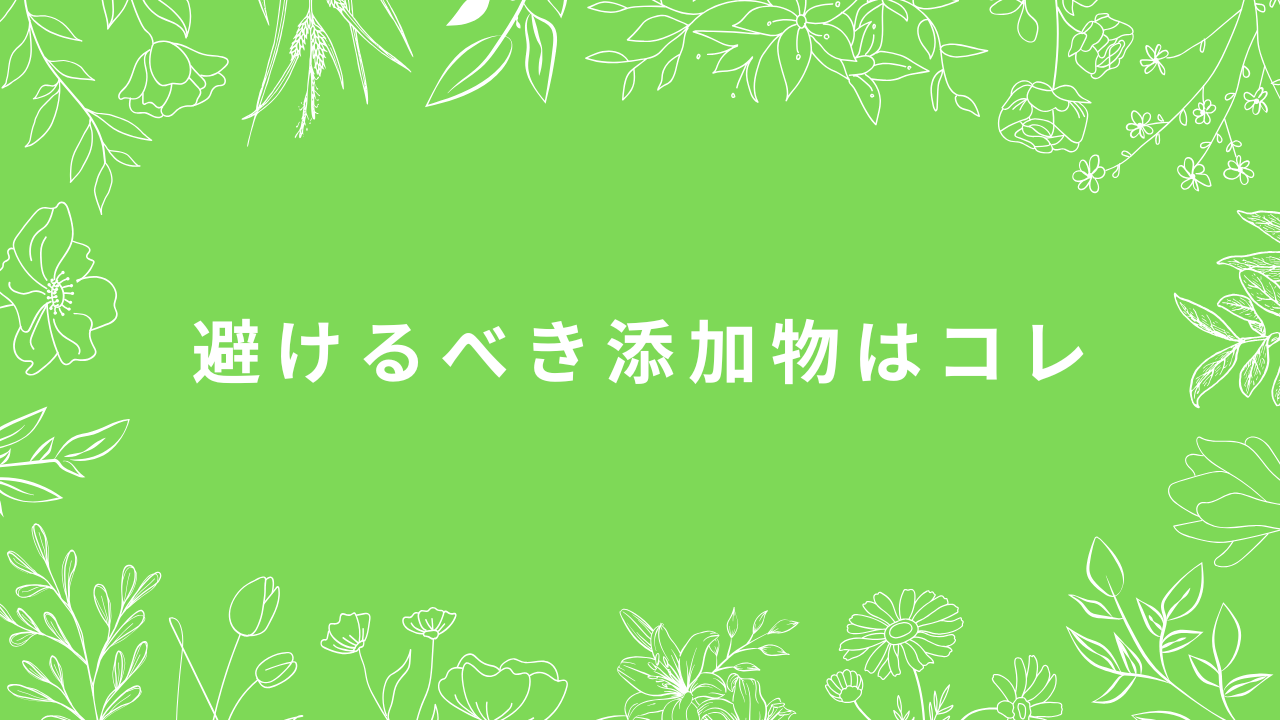
「無添加」という言葉を聞くと、体に良さそう、安全そう、というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。スーパーやコンビニでも「無添加」をうたった商品が増え、健康意識の高まりを感じます。しかし、現代社会で完全な無添加生活を実現するのは、実はとても難しいのです。
本記事では、無添加生活が厳しい理由と、それでも「できるだけ避けたい添加物」を紹介します。完璧を目指すのではなく、日常生活で無理なく取り入れられる知識を身につけていきましょう。
無添加生活が難しい理由
現代は大量生産・大量流通の時代。食品は工場で作られ、何百キロも離れたスーパーやコンビニに並びます。もし添加物を一切使わなければ、食品はすぐに腐敗してしまい、安全に流通させることができません。
また、消費者のニーズも多様です。
・見た目の美しさ:鮮やかな色、均一な形を求める
・保存性の高さ:日持ちする方が便利
・価格の安さ:コストを抑えたい
これらを満たすために、添加物はある意味“必要悪”として存在しています。つまり「すべての添加物が悪」という考え方は現実的ではありません。

避けたい添加物4種類
それでも、できるだけ体に負担をかけたくないと考えるなら、まずは下記の添加物から注意してみるのがおすすめです。
1、合成着色料(赤色102号など)
お菓子やジュース、漬物などに使われる合成着色料は、原材料欄に「赤102」「青1」など色と番号で表記されています。海外では一部の合成着色料が使用禁止になっている国もあります。
特に子どもは体が小さいため影響を受けやすいとされ、アレルギーや多動傾向との関連も指摘されています。着色料は見た目だけの問題なので、できるだけ避けても生活に支障はありません。
2,発色剤(亜硝酸ナトリウム)
ハムやソーセージ、ベーコンなどの加工肉に使われる発色剤は、肉を鮮やかなピンク色に保つためのものです。しかし、亜硝酸ナトリウムは体内で「発がん性物質ニトロソアミン」に変化する可能性が指摘されています。無塩せきハムや、発色剤不使用のソーセージを選ぶことで摂取量を減らせます。色が少し茶色っぽくても、それは自然な証拠です。

3,合成保存料(ソルビン酸、安息香酸Na)
長期間保存するために使われる合成保存料。ソルビン酸や安息香酸Naはカビや菌の繁殖を抑える効果がありますが、長期的な安全性については議論が続いています。
冷蔵保存や早めの消費を心がければ、保存料に頼らずとも食中毒リスクを下げられます。特に小さなお子さんが食べるものは、保存料不使用のものを選ぶと安心です。
4、漂白剤(亜硫酸塩など)
かんぴょうや干し果物、えびなどの下処理に使われる漂白剤。見た目を白く美しくするためのもので、摂取しすぎるとビタミンB1の破壊やアレルギー反応を引き起こすことがあります。
「漂白剤不使用」と書かれた食品を選んだり、自然な色味のものを選ぶことで摂取量を減らせます。

無理なく取り入れるコツ
無添加生活を目指すと、つい「これはダメ、あれもダメ」と神経質になりがちです。しかし、ストレスも健康に悪影響を与えます。大切なのは、完璧ではなく“できる範囲で”選ぶこと。
・原材料表示をチェックする習慣をつける
・家ではできるだけシンプルな調味料を使う
・加工食品を食べる頻度を減らし、手作りを取り入れる
・外食では細かいことを気にしすぎない
このようにバランスを取ることで、無理なく続けることができます。
まとめ
現代社会で完全に無添加生活を送るのはほぼ不可能です。だからこそ、まずは避けたい"添加物を知ること"が第一歩になります。
・合成着色料(赤102など)
・発色剤(亜硝酸ナトリウム)
・合成保存料(ソルビン酸、安息香酸Na)
・漂白剤(亜硫酸塩など)
これらを意識するだけでも、日常の食生活は大きく変わります。健康的な食生活は、完璧よりも継続が大切。あなたと家族の体を守るために、今日から少しずつ取り入れてみてください。